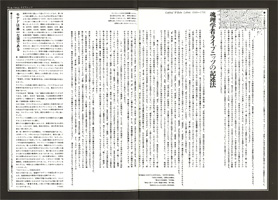ミュージシャン・文筆家 山崎春美さん
異端児の激白
「どうして工作舎に行ったか」なんて35年前のことを聞かないでくれ

工作舎に現れた春美さんは、遊塾同期の米澤敬編集長に別用があった。米澤編集長に、そのままインタビューに参加してもらう。
—— 『遊』の頃についてお話しください。
山崎春美 当時は『遊』の2期だったわけですが、言葉遊びで「遊術」というのを書かせていただいた時に、舎内ですれ違った松岡さん(正剛、工作舎『遊』編集長)に、「プエル・トリコじゃなくて、プエルト・リコだよ」と指摘されて、「まさか! またまた、そんなコト言って!」と一蹴して信じなかったことがあります。松岡さんも流石に呆れて「いや、そうだって」と言われたんですが、(担ごうったって、その手にゃ乗りませんよ)みたいにその場を去ったことが忘れられません。なんの根拠もないし、結局、実際には直したはずですが、どうして、ジョークで言われただけと思い込んだのかわからない。
そうかと思うと、「遊諧十傑」といういろんなベスト10を選ぶ頁があって、その中で「パンク・ロック」をやって、と言われて、持って行ったら、「うーん、ニューヨークばっかりだね。『NYパンク・ロック』にするか」と言われて、実際2位から10位まではアメリカのバンドばっかりだったんですが、「いや、あの、1位が『セックス・ピストルズ』(イギリス)なんですが」と言うと「あ、そうか…。んーと、まぁいいか」となったこともよくよく憶えています。
あと、工作舎にタモリを、いわば「拉致」してきたときのことです。その「こと」があった3年くらい後から「笑っていいとも」の前身番組がはじまりましたから、2014年3月末に終わるまで30年以上ずっと、全平日にTV生出演し続けるより以前の話です。要は、NHKを出てきたタモリを数人で取り囲んで、まぁまぁとか言いながらタクシーに乗せて、渋谷松濤にあった工作舎まで連れてきた…というか連行しちゃったんです。もちろん待ち構えていた松岡さんはじめスタッフが丁重に、「やぁ! これは! いらっしゃいませ! どうぞ、どうぞ。お待ちしておりました!」なんて、もてなすわけです。
天井まで届く本棚にびっしりと並んだ本を、驚き呆れたみたいに、でも興味深げに眺めていたタモリに座ってもらって、かくして土星の間での松岡さんとの対談が実現しました。わたしもその場にいたわけで、テープ起こしの名前にはいっているはずです。いざ帰る段になりまして。皆してぞろぞろと玄関までお見送りに行って、なんとなくぼーっとしていたら、そんなわたしの後頭部を松岡さんが押さえて前に倒されたんです。(コラ!礼をせんか!)(ちゃんと挨拶しなさい)とお辞儀させた、というかお辞儀させていただいたわけです。当時のわたしは、まだっていうより、もう「20歳(はたち)」なんですが、いかに子どもだったか!どんなに幼稚な若者であったか。

『遊』組本「は組」
—— 『遊』別冊組本・冗談本「は組」で、タモリと松岡さんが対談する「めばえ」という企画になったときの話ですね。そのとき、どうでした? 大物感があったんですか?
米澤 松岡さんのほうが堂々としていて、あえて言うなら大物っぽい。
山崎春美 大物感というのもひとつのスタイルだから、タモリは大物とかの感じじゃないですよ。
米澤 ふつうのおじさん。
—— 気さくな感じですか?
山崎春美 たんたんとしていた。まあまあ、ちょっとちょっと、って誘拐されるみたいに連れてこられたのに、明らかにその不条理を楽しんでるふうだった。
米澤 オーラという感じはないね。
山崎春美 オーラを消すほうがうまいんじゃないですか、あったとしても。
—— それって逆にすごいですね。
山崎春美 いまのタモリの話は、どんなに昔の話をしているかというリアリティをお伝えしたかったわけですが、それと同時に、工作舎がどんな風に見られていたのかについて、お話したいと思います。
最近、こうして活動を再開して東京にいて、会う人会う人が30年ぶりとか、『昔からずっと読んでいました!感激です!』といった方がいらして、それはそれで、ほんとうに有難く恐縮至極なんですが、たとえば間章亡き後の即興音楽界の最終砦を担うべき竹田賢一氏(『インプロヴィゼーション』デレク・ベイリー著の翻訳者)もやはり一昨年、初の単著を出された(『地表に蠢く音楽ども』月曜社)、そんな因縁から、一緒にトークイベントをやらせて頂きました[2013.10.19 ジュンク堂書店池袋本店]。『ミュージック・マガジン』でわたしに「めかくしジュークボックス」をやってくれた松山晋也くんに司会になってもらいました。松山くんは同い齢なんですが、竹田氏がちょうど10歳上で。
で、トーク後の質疑応答となって、当時を知る人に「なぜ工作舎に行ったのか?」と訊かれたわけです。
若い人や御存知ない方には、どういう趣旨の質問なのか、その「なぜ行った、どうして行ったんだ!」という、ややもすると詰問調でもあり得る部分にどんな意図が込められているのかわからないと思いますが…。
普通に考えたら単純な質問ですよね。わたしだって、
(ちょうど演っていたバンド「ガセネタ」が、リーダーだったギタリストの一方的な都合で解散したばっかりで、ぽっかりいろんなことが空いてしまい…)とも言えたし、あるいは
(そんなこと、いかにも、もっともらしく仰って御満悦の体に見えますけど、じゃああんた、当時オレより何才も歳上やったわけで、いまこの場で質問するんやったら、もっとあんたの質問意図を、いまはじめて聞いている人にも解るように意図が伝わるべく、しっかり訊いてくれや。ほしたら答える。答えてやるわ、偉そうに、でもなんでも。要は当時、『あんなカリスマ的な(印象の拭えない)松岡正剛のところに、長かった髪まで切らされて、しかも、そこで率いられている連中と集団行動まで取らされるのまで厭わず入ったんや。俺は××○○…だったから絶対行くものか、行くまいと思い止まったんだよ!』とか、知らんけど、御自分の主張を述べたらどうやねん!)とも言えたわけやけど、横に意見を異にするかも知れない竹田さんも居たりしたわけで、あえて控えて、わたしの本質的な性向だけをその場では述べて、そこは場を取りなした、なんてこともありました。当時は当時で、今からすれば熱血的とも根性主義とも取れる、逆に言うと、表現が適切かどうか、いずれ白熱した熱い関係と言っていいのか、切羽詰まる周辺事情もあったわけです。★註
—— なるほど。春美さんの「本質的な性向」というのは何でしょうか?
山崎春美 そのトークショーでの録音が残っているはずなので、いずれは本も刊行する予定だし、うろ憶えでしかないので、もしかせずとも、まるっきり異なった物謂いかも知れないですが、そこを省みずにわざわざ発言する無謀を、この場であえて自らに課してご披露できるとすれば、一言で言うと、自己投棄です。自己投棄を許してくれる、受け入れてくれる場所を、もちろん、それだけの価値のある場所にしか投棄しないわけで、当時は、そういう場所にしか行きたくなかった…。とはいえ、それはそうで、その通りなんだけど、それにしても35年も経ってまだ、そんな質問があるなんて、工作舎恐るべし(笑)!というか、業が深いというか、ある種、罪深いとも言えるのか。結局この時は、なんて答えたんだっけか。言葉上はもっと柔らかい表現で言ったはずですけど。
先だって工作舎を定年退職された森下(知)さんに、DOMMUNEの『デレク・ベイリー』刊行イベント[2014.2.17]後、「『遊』の頃は、あちこちから偏見の目で見られて大変だったでしょう?…」みたいなことを聞いたら、「偏見とか、もうそんなレベルじゃなくて、そりゃあ凄くて…。」と。 『遊』や工作舎への世間一般からの誤解は感じているんですか? 松岡正剛という、いわゆるカリスマ的な人が抜けた後ですから。
—— 普通の出版社になっちゃったね、とは言われます。そのあたりも含めて、ちゃんと見直したほうがいいんだろうと。私は93年に入社しましたが、工作舎は『遊』時代とは別の会社と感じています。
米澤 普通の会社にしようと頑張ったんだよ。でも普通の会社になりきれなくて、儲からないという話。
—— ここにきて米澤編集長が松岡さんの本『にほんとニッポン』(2014年10月刊行)を出すということで、きちんと覚悟して『遊』と向き合って、読者に対してアピールできるかわからないけれども何かうごめいてみようかなと。
山崎春美 そういうことでしたか。
—— 『遊』をリアルタイムで読んでいた赤田祐一さん(#003)、古本で知ったばるぼらさん(#004)と、それぞれ違う観点からお話をいただきました。春美さんはそれこそ『遊』の中で活動されていたので、思うままに語っていただくのがいいのかなと思いました。

山崎春美 この間、『デレク・ベイリー』刊行記念の新宿ブックユニオンでの、木幡和枝さんと大熊ワタル君のイベント[2014.1.17]に行ったときのことです。打ち上げの途中で灰皿を取りに行って帰って来たら、木幡さんが「思い出した、山崎春美だ!」って。それまでずっっと喋ってたのに(笑)。木幡さんは誰だかわからずに話してた。
—— 『遊』の頃は木幡さんとの交流はどうだったのですか?
山崎春美 ボクはRチームだったから。
米澤 木幡さんはFチームで、Fチームはちょっと近付き難い感じがあった。
山崎春美 だってお金稼いでます!って感じ。直結して。
米澤 いちばんプロっぽかった。広告代理店と仕事をしているから、背広着てネクタイして普通のスーツを着て。Fチームはわりと洗練されたような感じの人が多かった、社会的にみてね。
山崎春美 荒俣(宏)さんがRのミーティングにふつうに参加してた。とにかく図体がデカいから。毎年まだ身長が伸びてた、とか。あの79年は最高に密度が高かった。
米澤 毎日何かしらあったよね。
山崎春美 凄かったよね。だからあの陣容で2期がもし続いていたらとは思っちゃう。杉浦(康平)さんの関わりが低くはなっていたかもしれないけれど、フォーマットは杉浦さんだったし。
米澤 だから2期は最後まで密度感を保つことができた。3期になって、きのうも松岡さんとその話になって、2期を続けていればもう少しよくなったと。
—— なんで2期をやめちゃったんでしょうね?
米澤 ひとつは隔月でしょ、第三種郵便をとるには年間最低10冊出さないといけない。
山崎春美 流通を日販、トーハン、栗田、大阪屋、そういう取次が仕切っているんですね。
米澤 組本「ち」「は」「へ」があって、なんとか10冊。隔月では広告は難しい、と営業で言われていたんだと思う。月刊にすれば広告も入るし、経営が安定するだろうし。ということで月刊にしたんだと思う。松岡さんもけっこう疲れたんじゃないかな。
山崎春美 時期尚早だったのかな。1期は内の時代で、内と外とが浸透圧あるのが2期で、3期はついに、という言い方がよくされていますね。
米澤 3期は大衆路線に走った。打って出るための作戦として松岡さんはああいうフォーマットで、ああいうくくりでああいうデザインでやっていって、とくに若手のオレとか、宮野尾(充晴)、後藤(繁雄)を前面に出していったほうがアピールするだろうな、という計算をした。松岡さんにしてはポップという感じなんだけど。
山崎春美 ポップというか単にレベルを下げているだけとさえ、よく言われた。ページがスカスカになっちゃった。
米澤 密度感はなくなるわ、迷いが前面に出てきているし、編集もデザインも。
山崎春美 2期が早すぎるくらいによかったんですね。それを今の人に話をしても伝わらない。「『遊』のここを見れば」と実物を見せて、少しはわかってもらえるかどうか。でもその当時の時代背景に生きていないし、誰も当然わからない。ベルリンの壁どころか、ソビエトがなくなるなんて思わない時代ですからね。
米澤 だから編工研(松岡さんの会社、編集工学研究所)の連中も、新宿での松岡さんとのイベント[「山崎春美のこむらがえる夜」第一夜 2014.4.11]に来ていたけれど、当時の工作舎だったら自分は1週間で辞めるだろうって言ってましたね。
山崎春美 それは何? 生活のこと? ブラック企業だと言っているわけ? ボクの周りでいうなら高杉弾(佐内順一郎・『Jam』『HEAVEN』初代編集長)とかはいいんだけれども、隅田川乱一(美沢真之助・『Jam』『HEAVEN』編集部の思想的中心者)さんがね。ファンだったのに、松岡さんに裏切られたと感じていたようで。98年に他界していますが。
美沢さんという人は、そんなに出しゃばるほうじゃないけれども、ものすごく一本、筋の通ったものをずっと持っているような人だったから『Jam』『HEAVEN』が成立した。雑誌のバックボーンだった。ビート族、ヒッピー、ロックはむろん、シリアスなことも書ける。『ダーヴィッシュの物語』(平河出版社)の翻訳と、死後には『穴が開いちゃったりして』(石風社)という著書もある。その美沢さんが松岡さんをそう思うなんて。
まじめにやっているというと変だけれども、俺がシリアスかどうかは別にして、人からの批判はずいぶんあったようです。
もちろん、尊敬して慕う人も多くて、遊塾生だったマンガ評論の永山薫(遊塾生時代は本名の福本)は何かのインタビューで、「尊敬しているのは松岡さん」と言っていましたね。
そういえば工作舎に行きだしてすぐに、「吉祥寺遊会」が、羅宇屋と、よりによってマイナーで開かれた。灰野(敬二)さんが、高橋悠治の息子の、当時は名前が「高橋ゆうじ」と平仮名でお父さんと読みは一緒で(現在は「高橋鮎生」に改名)、まだ日本語が拙かった彼の背中をバアーンって蹴ってみんなシーンとなって、そこへ「音楽はゴスペルだ!」みたいなことを叫んだ。最近亡くなった故・中島(渉、遊塾生)なんかは、ボクの横に飛んできて、「この方はどういうお方ですか?」と訊いてきたりして、という状況で、ぱっと見ると松岡さんはハイライト(煙草)を口にもってってるところで、すごく斜に構えたというか、「それで?」つまり「So What?」という表情だったのを鮮明に憶えている。ニヒルというのか、あそこまで斜に構えた松岡さんを見たことが、わたしはあまりなかったんで、余計に強烈な記憶です。
灰野さんを間章の葬式に連れて行きましたからね。連れて行かれたのかもしれない。とにかく一緒に行って、みんな泣いたりしているお通夜会場である間さんの自宅に行って、ドアが開いて灰野さんがまず、「僕、不失者」って親指で自分を指差す。「不失者」ったって誰一人わからないんだけど、最近、名付けた自分のバンド名を名乗る。それで、背後に二人立っていたわたしと浜野(「ガセネタ」のギター。後に「不失者」ベース)を指差して、「こっち、ガセネタ」とバンド名で言う。中に入ると、中心に吉沢(元治、EEU)さんがどっかり座ってて、高木(元輝、EEU)さんが身も世もなく泣いてる。暫くして、「状況劇場です。このたびは…」って日本酒が届いて、次に「工作舎です。ただいま松岡が外遊中で…」って、高橋秀元さんが日本酒を持って来た。
とにかく灰野さんがああいう人なので、勧められる酒どころか、お茶も煙草も、右に倣って「結構です」と辞退して、ただただ隅っこにチーンと畏まって座っているよりない。で、時々「オーバードーズ(ヤクのやり過ぎ)だったから、もしかしたら骨も残ってないのかも知れない」みたいな話をこそこそっとしてる。あんまりいまも変わらないんだなって思ったのが、ここ一年強、友川(カズキ・白水社から自伝的な『独白録/生きているって言ってみろ』が2015年1月末に発売)さんと親しくさせていただいてるんですが、元はといえば西岡(文彦、遊塾生)さんの専売なのに、ちょっと悪いんですが(笑)、この間に一度だけ灰野さんとの対バンがあって、心配で、他の場所で別の用事があったのを早々に引き上げて行って、別に大丈夫ではあったんだけど、なんとなくこの吉祥寺遊会と図式が重なる。っていっても、35年経ってるのにね。
翌日が告別式なんだけど、このあいだ確認したら、やっぱり記憶が正しくて竹田(賢一)さんは通夜にはいなくて、でも葬式では、喪主ではないけれど、中心的に振る舞ってて、あれはどうしてだろう? 背筋が伸びていたからそう見えただけかな?
世の中で普通にやっていて、すごくカッコいいことなんて本当にあるのかと、いまやボクは疑問に思っています。つまり、どこに出しても間違いのない格好良さなんて、まずない。
阿木さんだってカッコいいだけではなかった。
—— 春美さんは、阿木譲さんが編集長を務める『ロック・マガジン』に高校生の頃、編集・執筆等を手伝ったんですね?
山崎春美 昔「こうして毎月何十万も印刷屋に払ったり、売上を回収したりしてれば人間一人食うくらいなんでもない」なんて言っていて、だけど行きつけの梅田の輸入レコード店の部長に聞くと、毎月30万円くらいのレコードを買っていて、どう考えたって、雑誌を作っただけでそんなにカネまわりがよくなるとは思えない。もっと後になって、町田(康)が芥川賞をとった後に、『日本ロック雑誌クロニクル』という本が太田出版から出て、自殺した中村とうようの『ミュージック・マガジン』、渋谷陽一の『ロッキング・オン』、ボクのこともちょっと載っていたけど、そのいちばん最後に阿木さんの『ロック・マガジン』が紹介されていて、まぁ赤田(祐一)君が『QUICK JAPAN』を出した版元だし。
そこで阿木さんが「日本のパンクは結論が出たわけだから」と言う。びっくりしたインタビューアが、「なんでしょう?」と聞くと、「町田町蔵[町田康のミュージシャン名]です。彼が答えた。曰く、あんなに無知だった奴がこうなる(おそらく作家としての成功を指すと思われる)」と。「これこそがパンクなんだから」と。まず、普通は意味がわからない。いつからパンクは矢沢永吉になったんだ? いや、世界の矢沢でも永ちゃんでもいいんだけど、そのサクセス・ストーリーがすべてだと言う人に訊きたいのは、かつては芸能界、ディランを、この嘘つきめと罵ったのはなんだったのか。かれらも世俗的には成功しているんだけど。かつて無料奉仕で阿木さんを支えてくれた女の子をスーパーで見かけて、「キミが男のパンツや野菜なんかを買って、男と一緒に嬉しそうに歩いているのを見て、悲しかった。キミがパティ・スミスを聴いていたのは、そんな世俗的な幸福だったのか?」と名指しで書いていたのは、なんだったんだろう? ということです。
もっとも、ボクが今でも反省していることもあって、それは高校生の頃に阿木さんの文章に手を入れちゃったことがあって、それは、「僕は…」と主語があって、ずらずらと文章が続いて、また「だから僕は…」と、また主語があって、明らかに文法がおかしいので、直してしまった。
「ハルミ、直すのはいいんだけど、僕の文体の魅力をわかっていないんだなあ」と言われて、その時は(この人、なにを言ってるんだろう)とわからなかったことが、さすがに今ならわかる。阿木さんの文章は、文法はおかしいけど奇妙なリアリティがある。正しい文法と阿木さんの文章のどちらを取るかと言えば、断然後者だろう。「僕は」が何回来ようが、その言いまわしに迫力が出れば、むしろ文法を無視するその無法ぶりまで含めて彼の魅力だろうとは思います。まぁ今みたいな時代になって、こんなことを言うボクの方が、よっぽどアタマが悪い感じですが、そうじゃないんだ。76年なんだ! その頃は、どんだけ堅い社会だったか知ってるか? とは言いたい。けど、しょもない馬鹿親爺に見えて来るから、この話はやめましょう。
そういえば、ある人が「保坂和志の文章を読んでいて何か既視感があるなあと思ったのが山崎春美がしゃべっているのに似ている。言っていることが最初はよくわからないんだけど後からわかる」と書いてくれていたんで、それで保坂和志の本を読もうとしたら、最初の3行目であきらかに文法がおかしい。誰が読んでも主語が途中で変わっている。三田格くんに訊いたら、「これわざとだよ」と。「わざとってどういう意味?」って聞くと、「賞をとったり、最初の頃は正しく文法通りに書いてたろうけど、今のはわざとだよ」と。別にこれはそれだけの話ですが。
人の粗をさがして生きているわけでもないので、それも本質のひとつだろうと思う。そういう小集団があってなんの矛盾もなく素晴らしいことを続けていくなんて、そんなことがあるはずないだろう。
アンジェイ・ワイダという監督は『灰とダイヤモンド』が有名だけれど、『大理石の男』ではレンガ造りの英雄が灼熱のレンガを持たされてヤケドして、そのへんから狂っていくんですね。左の共産主義社会なのに、そんな矛盾があらわれるのか。だからダメだというのはおかしい。あの頃は議論しない。議論にならないから。今はどうなのかな。ネット右翼も多いし、あまり考えずにいる。つまりヤンキーが多いってことですよ。大阪には多い。(忌野)清志郎なんかもうずっと70年代くらいから、反原発の歌を歌いながら商業主義と両立させてきた。いろいろな人がいて、いろいろなスタイルがあるわけです。後藤繁雄だって工作舎に来ていなかったらどうなっていたんだろう。当時、工作舎は運動体としての在り方が問われていたんですよね。その年代の人がみんなわかっているわけではない。どうですかね。
まぁわたしは変わっているかもしれないけれど。
ここで米澤編集長、バンド練習のため退室。
—— 遊塾で松岡さんと出会ったのは1979年。春美さんの活動再開後、2014年4月にはじめた連続イベント「こむらがえる夜」の第1回ゲストに松岡さんを呼んだのは強い想いがあったからですか?
山崎春美 79年って、35年も前の話なのに、まだこうして普通に話していることが異常だと思いますけどね。その頃にしかできなかった、松岡さんにものすごい実力があったからできたっていうだけじゃなくて、その時代にそこにあったものが特殊だったという気がしますけどね。それって同じやり方で明日からやるぞって言ってできるものではない。時代背景もあるし、言葉もそうでしたけどね。
—— 春美さんは最初は文章でデビューしたんですよね。高校時代から『ロック・マガジン』に寄稿されて。
山崎春美 『ホドロフスキーのDUNE』って映画が6月に公開されました。ホドロフスキーが『DUNE』の映画化を企画したけど頓挫したっていうドキュメンタリー。出演者がダリ、ギーガー、そうそうたるメンツ。最高の配役、製作陣。これって現実には存在しないですよね。結局『デューン』という映画はデビット・リンチが撮った。ホドロフスキーはその映画を「つらかったけれど一所懸命観た」と、そして内心から喜んだと、心から喜んだと、これは駄作だと。デビット・リンチの映画を。
話が行き過ぎですね、そういう魅力があるんですよ。最高のページがあるということではなくて、編集の在り方とか、よっぽど先駆的だったんですよ。もう『遊』の3期を終わる頃に浅田彰が『構造と力』で出てきた。浅田彰は「タコ」も見に来てくれたし、いろいろあるんですけれども、あのときに「『遊』は全部持っている、絶対手放さない」と、言っていました。そういう人は多かったですよ。
中森明夫さんがボクの本の書評を『週刊朝日』に書いてくれたんです。一回も会ったことはないけれど、存在は気になっていたと。55歳なんてまだ若いとほめてくれているんです。だけど帯に書いている二人(松岡正剛氏と末井昭氏)、こういうカリスマ的な編集者は自分は嫌いだと。そう書いていましたね。
ただ、どう言われても『遊』はわたしの原点のひとつです。よく、ここにしかないという言い方はするけれど、あれがあって、誰それがいて、それらが寄っているからここにしかないと言えたりもする。やっている人たちの力がここに結集できるような器をすごく上手につくっているんですよ。ものすごく先駆的で『遊』2期について言うと、たしかに表紙が西岡君になってから離れた人もいるかもしれないけれど、フォーマットは杉浦さんがつくったものだから。特に僕が入った頃に出た『遊』1008号で対の特集を立てるでしょう。特集「音界+生命束」。このときは遊塾がはじまったのと期をいつにして、3期を構想しはじめたからだと思うけれど、座談会をやりはじめているんです。3回の抽象的な特集。『エピステーメー』ならあるかもしれないですけれど、「音界」と「生命束」を対にしてわかるか、1009号の「世界模型」と「亜時間」ってわかるか。座談会は、1008号が生命の話、次の1009号が時間の話で、とうとう第3回1010号が形態をテーマにして終わりになった。○○○、×××というしかないんだと。
その思想に傾倒したんじゃなくて、読者やスタッフのエネルギーを上手に集めてくれた。それは、経営者が小手先で全員に毎朝eメールを出して士気を鼓舞すればいいというものじゃない。
松岡さんはその後、編集学校をつくって教育にいったでしょ。遊塾は教育的かもしれないけど。松岡さんが遊塾でつくったレジュメがそれはすごい。章立てをしているわけですよ。『千夜千冊』は本になって見出しの工夫がされている。けれど『遊』2期のような立て方はしていないじゃないですか。存在に返すから。これが出る前に『遊』1期9号10号「存在と精神の系譜学」では、ピタゴラスからマンディアルグまで数多の思想家たちを綴っている。誰なんだろうというようなあまり名前を知られていない思想家がいても、横組の補足でフォローしてくれる。メインの説明が縦組で、すごい粋なデザインですよね。
—— 『遊学』というタイトルで中公文庫になりました。補足はなくメインの説明だけですが、高山宏さんが解説で『遊』のレイアウトを絶賛しています。
—— 工作舎との再交流は、去年のセシル・テイラーの来日公演ですか?
山崎春美 休憩時間にみんな席を立つ、するとずらーっと席が空いて。ボクは2Fにいたので、1F席がどうなっているんだろうと、下を見ていたら田辺(澄江、工作舎)さんと目線があった。
—— 公演会場では石原(剛一郎、工作舎)も『ベイリー』の予約活動をしていて、それ以来交流が復活したのですね。吉祥寺のサウンド・カフェ・ズミでの「ベイリーを聴く会」の受付もしていますね。ベイリーはどうですか?
山崎春美 あの本で大変興味深かったのはベイリーがワーキングクラスということ。ビートルズはリンゴ・スターだけが本当のワーキングクラス。ジョン・レノンはあんなシリアスなのに、『イマジン』の裏ジャケットなんて豚をもって写っていて、ポールが『ラム』というレコードで羊を出しているから当てつけでやっている。ビートルズ解散後のジョンの最初のアルバムには「ワーキングクラス・ヒーロー」という曲があって、ポール・マッカートニーが「誰がワーキングクラスなんだ、おまえは違うだろう」と。多少はコンプレックスがあるんでしょうかね。だからもしドラマーが、ピート・ベストだったら、ビートルズは成功していないかもしれない。
デレク・ベイリーも完全にそう。あんな皮肉っぽい性格はフリーミュージックにいちばん合わない。ミルフォード・グレーブスみたいな人がフリーミュージックをやるのはなるほどってみんな思うでしょ。でもそうしたらアフリカのナショナリズムと言えなくもない。黒人の問題、あるいは南北の問題はふつうにあるけど、今でも世界人口のかなりの人は飢えているわけだから。そういうものは文化との関係でいくと、ミルフォード・グレーブス的なもの、スポンティーニアスでというのは偏りすぎていると思うのね、いま生きている現実とは違う現実から逃避しましょうというのと変わらないじゃないかと思う。デレク・ベイリーがいなかったらどんなふうになっていたのかなというのもありますよね。デレク・ベイリーはいわゆるスタジオミュージシャンみたいなものもやっているから、当然テクニックもあるけれど、テクニックという御託もあんまり言わない。やっぱり日本人はそういう逸材をとりあげるのがうまい。
—— 春美さんは『遊』組本「は組」で、十川(治江、工作舎)と田辺といっしょに編集をしていますね。「は組」はどうでした?
山崎春美 どうでしたって難しかったですよ。とてつもなく悩んだ。『エピステーメー』か『遊』かっていう雑誌でしょ。(「は組」特集テーマの)冗談って。「へ組(糞!あるいはユートピア)」や「ち組(ホモエロス)」は結論がないでしょ。「は組」は笑わせなきゃ。でも十川さんも田辺さんも笑わそうなんて多分思っていない。「ち」や「へ」といっしょにしないでよって思いません?
コツコツ頑張ったらできるもんじゃないんだから。「は組」は知識の延長線上でいいのか。人はなぜ笑うのかをやって、それでいいのかと。
—— 矛盾を感じながらつくっていたんですか?
山崎春美 矛盾? 笑わせられる本を作るのって、簡単じゃないんです。これはその後に作ったカセットブックの『どてらい奴』まで引きずりました。まぁ、もう決定していることなんだから、やるしかなかったんですね。

—— ところで『天國のをりものが』が刊行できたのも河出書房新社の編集者の熱意があったからですね。
山崎春美 最初に雑誌の『文藝』に原稿用紙30枚程度1本書いて、それから本(『天國のをりものが』)が出て、今また『文藝』に100枚書いています。もう書き終わっていないといけないんですけれど、まだ途中。文章を書く以外に道がない。ボクなんて。
—— ミュージシャンとしてはどうですか?
山崎春美 その可能性はない。数が決まってます。キャパがそれ以上なかなか増えない。文章以外にも『アックス』(青林工藝舎)では漫画みたいなものも描いている。
要するに町田が芥川賞をとっちゃいましたからね。頼むからこういうのだけはやめてくれ、というものを書いていますね。なぜ絶交したかはいろいろあるんですけど、80年代の終わりくらいまでは一緒に活動していて、「INU」のギターをやっていた北田昌宏とボーカルの町田で「至福団」というバンドを組んで、北田が音楽担当。『どてらい奴』を発表したとき(86年)は、まだバンドブームがくる前。この『どてらい奴』のブックレットは全部ボクが担当して、町田はタレントでした。特異な顔だし、まあいいんだけど。吉本ばななに気に入られちゃって。
町田については東大や京大を出た若い編集者におべんちゃらを言われていい気になって、サイテーだというのは聞いたことはありますが。そりゃ布袋は身体デカイし、ああいうヤツだけど、蹴り出されて[布袋寅泰に殴られて町田が訴えた事件]腹立ったからって、ふつう警察に電話するか? 典型的な根性悪だと、みんな言っていますけどね。まあいいんじゃないの。絶対、昔のイメージは出さないからね。
—— 作家活動について戻りますと、『天國のをりものが』の中には音楽評論・エッセイの他に、フィリップ・K・ディックのような幻想な短編も収録されていますが、これから書いていく作風はどのようにするのでしょうか?
山崎春美 もっと変なものになったらいいんですけど。なかなか難しいんです。河出書房新社の担当はテーマも内容も何もなくていい、なんだったら昔の古典を基にしたらと。ボクは文体が変わった書き方しか絶対しないので。だからH・R・ギーガーの追悼文を依頼されたのも、ボクならありきたりの追悼じゃないものを書けるから、なんて言われた。
—— 文章だけではなく、春美さんの存在そのものを世に出したいという想いもあったのでは?
山崎春美 ボクはしばらく表舞台から離れて、もういないような存在だったので。面白いと思ってくれているんだと思います。
ボクは1958年生まれなんです。竹田賢一さんが1948年生まれで10歳上なんですね。竹田さんは最初坂本龍一さんと「学習団」をつくった人。鈴木いづみは49年生まれで、阿部薫が死んだ9月8日の晩に竹田さんに電話をかけて、「薫が動かないんだけどどうしたらいいんだろう」って、あの鈴木いづみが、普段は絶対にうろたえたりしないのに。「ボクのところなんか電話している場合じゃないから救急車を呼べ」と言ったそうです。
この世代には戦争があるんです。第二次世界大戦の影響、が絶対あるんです。ボクが小さいときに『忍者部隊月光』が流行ったんですが、登場人物は10人くらいで、敵と戦うと、一人、また一人と死んじゃうんですね。死んじゃうと人数が減った状態で次に進む。それは不思議じゃないと今は思うかもしれない。あの当時の世の中ってフィクションの中であまり死を想定しなかった。テレビという公共の器の中になるから。いわゆる戦後の民主主義のお約束のひとつですけど、現実では死んだら生き返ったりしないでしょ。その中で生きている。Life is just to die、ルー・リードの詩ですけれど、「死ぬために生きている」わけですから。カッコいいことをやるという時には、そういうのを見逃している。
例えば唐十郎はあんまりストーリーがわからないけれどカッコいい。いちばんカッコいいのは、パレスチナに行って公演したこと。パレスチナにいる日本赤軍は指名手配を受けているから、行くことも無謀だけど、役者は誰も現地の言葉は喋れない。それじゃ現地でやる意味ないでしょ。全部現地語に訳してもらった言葉を覚えて公演した。それはカッコいいなと思った。
若松孝二もカッコいいですよ。『天使の恍惚』というタイトルはもうこれはちょっと一語も抜けないなという気がしますけどね。タイトルとかそういうのが好きなんです。コピー的ではあるけれど。コピーというのは大変じゃないですか。企業イメージとかぜんぶ気にしなくちゃいけないし。コンセプトを打ち出せるくらいじゃないとだめでしょ。本当は詩のH氏賞をいちばんとりたかったんですよ。子どもの妄想ですよ。今思うと、70年代途中の『現代詩手帖』や『ユリイカ』でそんなにすごい詩があったかというとない、ない。闘争がないから。世の中に荒れ模様がないと、良い詩はできない。
「フールズ」というバンドがかろうじてまだあって、昔はよく「じゃがたら」と「タコ」とで、三大過激バンド・ツアーなんてやってたんですが、ここのリーダーの伊藤耕って、もう何十年も会っていませんが、前科六犯とかで刑務所を出たり入ったりしている。んー、シャブかな。なんでもいいんだけど、刑務所で書く詞はすごい良いんだって。出て来ると、あんまり良い詞が書けないんだって。ボクは前科ありません。おまけに、なにしろ巨人のV9が義務教育の6・3年と重なってるんでね。さっぱりわやです。
—— 紀伊國屋書店のイベントの際はじんぶんやフェアも選書されましたが、担当者は「春美さんは長いエッセイも書いてくれて、100冊も選んでくれて本当にいい人」と、それは感動していました。
山崎春美 松岡さんはその10倍も書いています。本を選んであとは好きにしてという人がいてもいいですけれど、こんなに書くヤツがいてもいいかなと思ったのと、「タコ」とか『HEAVEN』とか昔のボクを知っている人以外は、知らないのが当然だと思うので、そういう人にはアピールしなきゃいけないと言われて、それはそうかなと素直に反省して書いたんです。オレを知っているだろう、みたいに書くのは嫌だなというスタンスでやっています。まだ昔のボクを知っている人がいるギリギリちょっと間に合ったかな。
—— 長時間にわたるインタビューに時間を割いていただき、ありがとうございました。とりとめのない質問ですみません。インタビューがうまい人だったら、的を得た質問で本質をつかむことができるんでしょうけれど。
山崎春美 それってひとつの本質が出ているだけじゃないですか。本質ってひとつじゃないでしょ。ま、いいんだけど。

そういう忘れ難き「時代の熱気」があったからこそ、先日出版された『工作舎物語』のような本の出版がなされるのでしょう。だから、『工作舎物語』の出版自体は、変な言い方だけど「正しい」と云うか「然り、ごもっとも」です。
ただね、だとしても、コトあの本そのものに限って言うなら、あまりにもいい加減過ぎです。つまり、いったい御自分の青春期の、それこそ(熱い想い)を語りたかったというのなら、それはむろんよく解るし、でも、だからこそもっと丁寧に裏付けを取るなり説明責任を果たさないといけない。人によっては、山崎春美にそこまで言われたないわ!と思う向きがあるかもしれませんが、それはそれで言われて構わない。触ればヤケドしそうに熱い60年代と、ニューアカのブームに象徴される80年代初頭に至るまでの、まさしく『遊』の発刊されていた70年代とはいったい何だったのかは、そのくらい真剣に問われているんだと想います。『工作舎物語』については『アックス』103号に書評を書きましたから読んでください。


彼に言わせると、「60年代については数多くの書物があり、80年代以降も、ニューアカをはじめとしたたくさんの言説や本が存在するが、その間が何もない、わからない。あんた(=山崎)どこに行ってたんだ?」
ここまで言われれば、人間としてちゃんとそこの陥没部分を、最低限には説明しないと、とは思います。
ピケティがいま話題ですが、彼が提出したのは、膨大なデータとその説明、及び彼の持論です。そして、あくまでも「これによって議論が活発化することを願っている」としています。