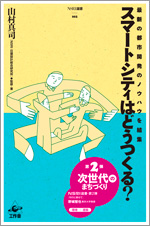『スマートシティはどうつくる?』より

中国天津于家堡金融開発
1月新刊、NSRI(日建設計総合研究所)選書シリーズ第2弾、『スマートシティはどうつくる?』が好評です。本書は、世界の都市が取り組む「スマートシティ(スマートコミュニティ)」を紹介しています。
上の画像は「中国天津于家堡金融開発」のCG図。日建グループが手掛けた海外・都心型業務中心地区開発の例として、本書巻頭カラー口絵に掲載されています。低炭素都市として開発中のプロジェクトで、食品廃棄物から電気、熱、ゴミ回収車両の燃料へのエネルギー転換、緑の連続による風の道ネットワークなどの提案が記されています。
日本国内の例としては、柏の葉キャンパス(千葉県柏市)や、湘南T-SITEがある藤沢SST、地区内で発電する日本橋スマートシティなども紹介。
ところで、この「スマートシティ」とは何でしょうか? 経産省では「ICT技術を有効活用して、都市関連インフラを効率的に運営し、生活を快適かつ利便性を向上させることが可能となる都市」と位置づけています。
もともと「スマート」とはアメリカの電力インフラに端を発します。安定した送電のための監視・制御システム「スマートグリッド」を軸に発展しました。
一方、欧州では、既存電力ネットワークに太陽光発電等の再生可能エネルギーを系統連携するかたちで普及し、省エネ、低炭素を目的とした「エコシティ」の次のコンセプトとして捉えられています。
日本では、国の政策に基づいた「エコタウン」などの呼称が、現在の「環境モデル都市」「環境未来都市」へと連なっています。さらに、中国や中東諸国など新興国では、雇用や新規産業の創出まで含めた包括的な目的を持ちます。
このように「スマートシティ/スマート化」は定義するには、あまりにも多くの課題と向き合わなければならず、標準化が急がれる“現在進行形”の概念です。しかも、計画が止まったり大幅な見直しを余儀なくされるなど、リスクや課題を抱えています。本書ではその現状、課題、開発例をコンパクトに紹介しています。ぜひ、お読みください。