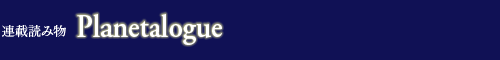第24回 町田一氏による橋本由美子先生追悼
2017年4月20日昼頃、前日夜に送信されていた酒井潔先生からのメールで18日に橋本由美子先生が亡くなられたことを知った。25日の告別式の出棺のとき、御主人は、橋本先生が18日午後7時に旅立たれたと話されていた。遺影はワインを片手に微笑むチャーミングな姿であった。
2年前の夏に癌の告知を受けて入院治療し、昨年復帰されて煙草を吸っているとの噂を聞いて安堵していたのだが、それも抗癌剤を断ってのことであったらしい。
先生からの最後のメールは昨年10月25日のもので、「11月に東大で行われる日本ライプニッツ協会大会にいらっしゃるのであれば久しぶりに一杯どうですか」、と尋ねたメールへの返信であった。ある出来事について回顧されてから、一転、「驚かないでくださいね、実は今月再発して、緩和ケアになりました。授業なども今月で終わりにします」と切り出され、聖路加病院の緩和ケア外来に通院しているということであった。「もうライプニッツも読んでないのですけれど、今年の前半、心身のテーマと出来事のテーマを隔てなければならないのでは、と考えていました。出来事は、命題ですからね」と続き、「頭を使うのに、良い季節です。愉快な毎日を!」と結ばれていた。覚悟を決めたことばであるように思えたので、これ以上のやり取りは断念した。
橋本由美子先生は1956年鳥取に生まれ、大学は京都に出て同志社大学に入学。
中央大学の大学院で本格的に哲学を修めることになる。ここで、所雄章と木田元という対照的な二大巨頭の門下となったことが、彼女の哲学におおきな影響を及ぼしたと考えられる。翻訳を通した出版社とのつながりはおもに木田元の紹介によるものという。
中央大学では先生主催の読書会を続けられ、これはと見込んだ学生を慶應や東大などの大学院におくりこむことも多々あり、現在も哲学の研究生活を継続している橋本塾生はかなりの数にのぼる。お気に入りの学生たちとピクニックに行くこともあれば、「合宿」と称して別荘に招待しては楽しく過ごす、姉御肌で学生たちからの信頼の厚い先生であった。
知り合った当初、先生のことを自分と同年代の人物と思い込んで、「呑もうぜ、橋本」などと呼び捨てにしていたが、ご本人から注意、警告ないし恫喝されたことは一度もない。かなりあとで、一回りほど年が違うことがわかって驚いたが、その後も、「橋本さん」で通した、ほんとうに希少な友人であり、学会でも話の通じるほんの一握りの中の一人であった。
告別式の後、上大岡の蕎麦屋で小川量子先生(スコトゥス研究の大御所で橋本先生とは30年来の友人)と佐藤真基子先生(アウグスティヌス研究の中堅)とで先生を偲んだ。
橋本先生と初めて知己を得たのは小川先生を介してである。小川先生が慶應義塾で主催していたスコトゥスの読書会に橋本先生がお見えになり、同じライプニッツを読んでいるということで交遊が始まった。15、6年前か、さらに前のことであろうか。当時は、中川純男先生もご健在で、研究会やら何かにつけては橋本先生ともどもゼミの連中と蕎麦屋や激安イタリアンなどで終電間際まで他愛もないことや研究上のまじめなことを話し続けることが多かった。彼女はかなりの聞き上手で自分から話をしたがる人ではない。ただ、気に入らないか、あるいは見限った人物については(教員を含めて)、「哲学に向いていない、やめたほうがいい」、「学生を指導できる力があるとは思えない」など、小津映画の三宅邦子のような穏やかな口調で切り捨てた。
あるとき、そんな呑みの席で、「哲学以外にどんなものを読むの?」と聞かれたことがある。「山田風太郎」と答え、「橋本さんは?」と聞き返したら「村上春樹」ということであった。村上春樹とは、今思うに橋本先生にふさわしい。橋本論文において、初期村上春樹のごときどこか乾いた文学的な匂いを感じるのはわたしだけではないであろう。翻訳の名手であったのも、古今東西の文学に通じその一文一文を味わい尽くし、咀嚼しておられたからであるとも考えられる。
2014年11月8・9日に中央大学で行われた中世哲学会大会が、直接お会いした最後の機会となった。大会初日に、「翻訳のことで、お話したい」と連絡を受けた数人が中央大学の一室に集まった。ライプニッツ初期の論考集「最高権論」(De Summa Rerum)のうちいくつかを共訳で出版しようというのである。‘Summa Rerum’とは、本来、ラテン古典の文脈では全世界ないし世界全体を、法学の文脈では最高権を意味する多義語であるが(場合によっては「神」そのものを指すという説もある)、アカデミー版に基づくこの論集にはスピノザにかかわる論考が含まれている。これを先生が選ばれたのは、スピノザ抜きにライプニッツはわからないという見解をお持ちであったからであろう。
橋本先生の翻訳のなかでは、白水社クセジュ文庫の『ライプニッツ』(1996)は何度も手に取った。訳者あとがきに次のような解説がある。
「ライプニッツの体系は哲学にとどまらず、数学・論理学・物理学・法学・神学等多岐にわたり、そのどれからでも体系全体へ近づくことができる反面、体系の全貌を一挙に照らし出すことは不可能にひとしい。むしろ、このような多様な学において同じ原理が用いられ、その原理をたどることで別の学への通路が開かれるというところに、ライプニッツ思想のきわだった特徴がある。」
これほど簡潔にライプニッツの体系の本質を言い当てた文章を他に知らない。「同じ原理」とは、矛盾率であり、連続率であり、充足理由率である。
『形而上学叙説 ライプニッツ-アルノー往復書簡』(平凡社ライブラリー)も、河野与一訳(岩波文庫)とはまた別の読みを示しており、明らかな誤訳も訂正したと聞いている。ラテン語やドイツ語も読まれていたが、フランス語はとくに達者であられた。共訳の話をもっと具体的にすすめ、急いでおけばよかったと悔やまれる。
もう一つ、橋本先生との約束がかなわなかったことがある。2015年4月に上梓した自訳著『初期ライプニッツにおける信仰と理性』(知泉書館)の書評を先生に依頼していた。酒井先生の仲介で図書新聞に掲載されるはずだったものである。橋本先生に本を送ったところ、6月3日に以下のメールが届いた。
「今回の御本は、画期的な作品だと思います。この時代のライプニッツも新鮮ですが、ジャンルもこれまでの闇に光を当てるようなもので素晴らしいと思いました」。
「この時代」とはライプニッツがマインツで宮廷顧問官をしていた青年時代(1666 –71)、「ジャンル」とは神学・聖書論を指す。初期ライプニッツ研究は少なくとも日本では王道ではない。しかし、橋本先生は、あらゆる偏見から解放されておられた。時代区分や現代的視点などにこだわらず、核心は「哲学する」こととテキスト批判にあった。いとも軽快に中世、スピノザ、ライプニッツから、ヘーゲル、ドゥルーズまで縦横無尽に読みこなし、哲学されていた。
図書新聞から橋本先生に連絡のないまま7月になって、先生から、学生を含めた数人が自訳著を読みたいと言っているとメールがあり、数冊をまとめてお送りした。本の値段が高いのでその気のある学生がいればいくらでも買い取り分から差し上げますと伝えていたのである。
間もなく達筆で書かれた御礼の葉書をくださった。先生のお人柄がにじみ出ているので全文を写す。
「前略 先程、本が届きました。本当に有難うございます。書評についてはまだ連絡届きませんが、ノートとりながら途中まで読んだところです。難しく面白いです。学生たちには各大学で宣伝するよう、伝えておきます。いずれライプニッツ協会などで顔を合わせるとも思いますが。暑いですね! 例年のように猛暑となりました。疲れはしますが、強く青い空は良いものですね。またご連絡します。まずは御礼まで」。
こののち、先生は自ら図書新聞の編集者に連絡を取り、「書評の締切は9月末までということになりました」と知らせてくださった。
2015年の夏、「腫瘍が見つかったので、検査を受けている」との不穏なメールが届いた。8月24日のメールでは、腫瘍が悪性であったこと、早期ではないので「ちょっと厄介」であり、書評を辞退して別の「しっかりした人を紹介したい」と書かれていた。結びには、「また元気にライプニッツを読むのを励みに、しばらく休みます」とある。橋本先生はかならず回復し、またともに楽しく過ごせるであろうと思ったわたしは、書評の代打は断り、先生の復帰を待つことにした。
先生に書評いただきたかった理由は、他にもある。自訳著の原型は2011年度に学習院大学に提出した博士論文であるが、その構想を練り始めたころ、パソコンが壊れたと話したら、その翌週には中川研究室の机の上に橋本先生ご愛用の赤いノートパソコンが置かれていたのである。使い方もレクチャーくださり、このパソコンでようやくインターネットも始めた。自訳著の完成の源となったこの赤いノートパソコンの恩義をどうして忘れることができよう。
想い出は芋づる式に甦る。2011年3月、震災の一週間前に大阪大学で行われた科研費の研究会の帰り、二人で喫茶店に入り、何時間も他愛ない話をしていたのであるが、突如、「ライプニッツを引っ張って行ってくださいね」と真顔になられた。橋本先生はふざけた話をしていても急に何か核心を突くようなことを尋ねられることがあった。
2013年4月、酒井先生の呼びかけで、『理想』のライプニッツ特集の論文執筆者数名が箱根で合宿した。その帰りのロマンスカーで橋本先生の冴えわたる人物鑑定を傾聴していると、やはり突如、わたしの論文の主題、信仰と理性の一致について「どうやって一致するのかしら」と直球を投げてこられた。理性による論証の区分の問題なのか(幾何学的論証かそうでない論証かということ)、信仰の対象の問題なのか(真なるものとは何かということ)を混同すると迷宮入りするとかなんとか答えたはずである。
橋本先生はしばしば神の問題について記している。たとえば以下の、実存思想協会編『道・心身・修行』(2014)収載の『ライプニッツ読本』(2012)の書評の一文。
「ライプニッツが弁護する神は、プロテスタント、カトリックに寄り添いながらもいずれからも距離を置いている。そうした神であったとしても、この神というファクターが除かれるならば、ライプニッツの体系は崩壊しなくともきわめて混沌としたものとなるだろう。…中略…一七世紀人であるライプニッツに定位するのなら、神なきモナドロジーは成立しないだろう。」
わたしは自訳著において、ライプニッツの神は普遍神学の信仰対象となるべき神ではあるが、そのモデルは、理神論者が求めるような神ではなく、歴史と伝統に基づくカトリックのそれであることを明かそうとした。このあたりのことをどのように評されるのか楽しみにしていた。なるほど、先生がこの書評で述べていることに間違いはない。ただ、「距離」とは何のことなのかが気になる。神のことを「形而上学的機械」と規定することもあるライプニッツは、教父や中世の伝統とは関係がない、近世固有の思想の持ち主であると断定する研究者もいる。しかし、これは誤りである。福音派の宗旨をもってはいたが、ライプニッツは三位一体、受肉そしてユダヤ・カトリックの説く同一身体の復活をキリスト教の信仰箇条として、生涯、容認していたからである。煉獄や実体変化(化体)についてのライプニッツの見解の一貫性についてはなるほど議論の余地はあるが、三位一体、受肉、身体の復活はキリスト教信仰の核心であり、これを容認する限りにおいてライプニッツの言う普遍神学の基盤はキリスト教でなければならないであろう。ここをどう考えるのか尋たかった。ライプニッツにおける、信仰の対象としての神とは何なのかということを。
最後になるがこの問題について橋本先生の見解を探り得る論考をとりあげる。
「ピラミッドの頂点」(『理想』691号2013: 特集ライプニッツ『モナドロジー』300年)の冒頭で先生は、「建築家としての神、それは完全な設計図を引く完璧な設計者である」と書いている。ここから、しばしば論じられる悪がなぜこの世界に含まれるのかという弁神論的主題の考察を通して、「神は創造をひかえることだってできた。創造しないこと、そこに矛盾はないからだ」と言う。しかし、「創造しないこと、これはあらゆる手を尽くしても避けなければならない」とも言う。なぜ、「神はその善のリスクをおかしても不完全な世界を創造する」のか。先生は「ここに〈おこない〉の神秘の一端があり、世界の創造という行為にはまさにこの意味で神の善が宿っているのである」と結論付けている。
創造が「神秘の一端」であるとは、まさに創造がキリスト教信仰に根差す問題であることを意味している。そして、先生は創造が何か論理的な必然性を伴う〈おこない〉であるのではないことを容認するが、同時に、この世界を創造せざるを得ない理由の根幹に「神の善」を見出している。神があえて「その善のリスクをおかしても不完全な世界を創造する」という〈おこない〉の理由は神の善性にある、ということである。
では、なぜ、神は悪を含む不完全な世界を創造するのか。そして、なぜ、その世界が「最善」でなければならないのか。神に見いだされる最善性から、創造されたこの世界の最善性を導く考えは何もライプニッツに限られたことではなく、教父神学、新プラトン思想を経由してキリスト教教理史において、とくにカトリックの伝統において垣間見られるものである。たとえば「可能世界」を創造の脈絡で導入するのもライプニッツだけではなく、トマスもそうである。しかし、トマスはこの世界が最善であるとは論じない。驚くほどドライに、神は無限に多くの可能世界を創造し得たのであるから、この世界が最善であるということは論理矛盾になると考える(菅原領二「トマス・アクィナスにおける可能世界の問題」『中世思想研究』第58号)。つまり、「最善」は極値であるがゆえに、これは「無限に多くの可能世界」と論理的に相容れないということである。「最大の自然数」が論理矛盾となるのと同様である。ここで想定されているのは発散する無限の系列である。
一方、ライプニッツは無限に多くの可能世界の中の「最善」を措定する。ここにはいわば収束する無限の系列が想定されているわけであるが、よく言われるように、「最善」は最悪を含むがゆえの最善である。橋本先生は、これを「最善という帰結的意志は、ほかの世界よりも悪が多いのではないが、ほかのどの世界よりも悪は世界全体を深く浸食している」と表現している。彼女によると、神の善はこの悪の「起点」として存在する。創造は必然的な神のふるまいではないが、「必然的に悪を含む」がゆえに神はその善を「リスクにさらす」のである。建築家としての神は、こうした悪の青写真をすべて見通していたがゆえに、この世界を創造するわけである。
しかし問題はまだ依然として残っている。なぜ神は創造せざるを得なかったのか。つまり、なぜ、現実世界はすでに存在しているのか。この理由を「神秘の一端」であると結ぶことは許されようか。これでは思考の、つまり、哲学の放棄ではないのか。ここがいまだわからぬところである。しかも、なぜ、「無からの創造」でなければならないのか。これは「わかる」かどうかの問題ではないのであろうが、いや、「問題」ですらないのかもしれないが、しかし、それで納得することはトマスやライプニッツ同様どうしてもできない。信仰と理性とは、問題設定そのものが破綻せざるを得ないのであろうか。
議論したいことはまだまだある。他愛のない話ももっとしたい。
しかるに、橋本さん、その姿は見えなくなったが、「魂の自然的不死」が正しいのであれば、現実世界の永遠性ですべて事足りる。
「死」はない。もしそうなら、冥福を祈る必要はない。いずれお会いできようから。

第1巻第2部「サロン文化圏」を気品ある日本語に
仕上げてくださった橋本由美子先生
(慶應義塾大学COE研究「ライプニッツ研究会」[2007〜]のWebより)
* *
日本ライプニッツ協会の次世代の担い手のお一人・町田一氏は、訳著書『初期ライプニッツにおける信仰と理性』(知泉書館)で論じられなかった「復活」について、「ライプニッツにおける身体の復活:教父的伝統と哲学的革新」(『中世思想研究』第57号 2015)で補足されているとのこと。第II期第1巻では「スピノザとの往復書簡」(共訳)、第2巻では「法学を学習し教授する新方法」(共訳)と「宗教の平和について」を訳されています。
(十川治江)